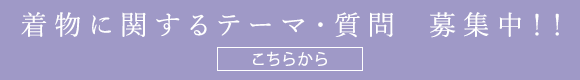〈西陣〉
2月にはぜひ訪れたい「北野天満宮」

底冷えのする京都の冬。寒いけれど2月になると、そこここで梅の便りが聞かれ、春への期待が高まります。梅の季節に必ず訪れたいのが北野天満宮です。菅原道真ゆかりの社ですから、境内には梅がたくさん植えられ、この季節には梅のほのかな香りで満たされます。学業の神様として受験生の絶大な人気を誇る天神様は、受験シーズンになると本殿にお参りの長蛇の列が出現します。
毎年2月25日の梅花祭には本殿の南の梅苑で、咲き誇る梅の花のなか、上七軒の芸妓や舞妓によるお点前が披露されます。ちょうどその日は毎月25日に行われる「天神さん」の日にあたり、境内や参道いっぱいに縁日の露店が並びます。焼き鳥やリンゴ飴、甘酒を手に骨董市をひやかすのも楽しみです。
梅の季節でなくても境内には見どころが多く、国宝北野天神縁起絵巻のある宝物殿をはじめ、土蜘蛛の伝承のある東向観音寺、秀吉の築いた御土居など歴史の深さを感じるスポットが満載です。
門前で食べておきたい甘味は澤屋の粟餅と天神堂のやきもち。境内の長五郎餅も有名です。藤野やとようけ茶屋など有名豆腐店もここの門前にあります。
「北野天満宮」の詳細はこちら
どこからともなく三味の音色が響く上七軒は、京都最古の花街
北野天満宮の東門を出るとそこは、花街上七軒の北西端。
祇園や先斗町など繁華街の花街に比べると、観光客も少なく静かでシックな佇まいです。碁盤の目のように直角に交差する京都の町並みには珍しく、斜め45度に道がついています。
西陣の旦那衆の社交場として栄えた上七軒は、花街としての歴史は京都でもっとも古いといわれています。上七軒歌舞練場では春には芸妓・舞妓衆による「北野をどり」が催され、華やいだ季節を迎えます。この歌舞練場は夏場になると庭園をビアガーデンとして開放し、芸妓、舞妓がお酌をしてくれる楽しみを提供しています。
上七軒でのお土産探しは、かわいいがま口専門店「まつひろ商店」でいかがでしょう。唐草模様のがま口を描いたのれんが目印です。
「上七軒歌舞会」の詳細はこちら
「まつひろ商店」の詳細はこちら
住宅地に突如現れる超ド級寺院「千本釈迦堂」
上七軒の北東すぐのところには「千本釈迦堂(大報恩寺)」があります。ここは国宝の本堂と、快慶作や定慶作の重要文化財の仏像がごっそりあるという、実はヘビー級のお寺です。ごく普通の住宅地の中に、国宝の建物が忽然と現れるなんて京都ならではの光景です。ここは建築関係者の信仰が厚く、境内には名だたる建設会社の奉納した玉垣が見られます。それはなぜかというと……。
この本堂の建築の際、棟梁を務めた大工の高次が手違いから重要な柱の寸法を短く切り過ぎてしまいました。頭をかかえる高次に妻のおかめは柱頭の枡組で補えば良いと助言し、窮地を救いました。けれども「女性の知恵で棟梁が大仕事を成し遂げたと言われては夫の恥」と上棟式を迎える前に自害してしまいます。今も新築の上棟式で御幣とともにおかめの面が掲げられるのはこの故事に由来しています。「千本釈迦堂」の境内には、おかめさんの功績を讃えるおかめ像が建立され、建設関係者の信仰を集めるとともに、夫婦円満のシンボルとして参拝者に親しまれています。
「千本釈迦堂」の詳細はこちら
京都一の桜の名所「平野神社」
さて、北野天満宮の北門を出て西に100メートル歩くと「平野神社」の朱の鳥居が見えます。ここは平安京を造った桓武天皇のお母様、高野新笠を祀っています。境内にはありとあらゆる種類の桜の木が生い茂り、一年を通して桜が咲いているといわれています。桜の季節には境内一面に仮設の座敷が設置され、神社丸ごとお花見の大宴会場と化す光景が見られます。お花見の期間は夜な夜な救急車が駆けつける珍しい神社となります。とはいえ桜の季節以外はひっそりとして参拝客も少ない穴場の名所。青葉の季節にはほんのり桜餅の香りがただよい、清浄な社域では、ときおりドラマのロケも行われています。
平野神社を西に抜けると西大路通に出ます。すぐ北には安産祈願で有名な「わら天神」、そのまた北には「金閣寺」 金閣寺からきぬかけの路をたどると「龍安寺」、「仁和寺」と怒濤の世界遺産三連発です。
「平野神社」の詳細はこちら
「金閣寺」の詳細はこちら
「龍安寺」の詳細はこちら
「仁和寺」の詳細はこちら
「西陣織会館」で着物情報を仕入れて観光へ
キリがないので西陣に戻りましょう。そう、北野天満宮、上七軒あたりは着物の聖地(?)西陣エリアなのです。各種のきもの体験のできる「西陣織会館」も近く、ここを拠点に京都観光するのも着物好きにはぴったりなのです。舞妓や芸妓、十二単の変身体験や手織り体験のほか、毎日開催される着物ショーや、西陣織の紹介など、多角的に着物を学ぶことができる施設となっています。着物を着ているだけで、各所で割引が受けられる「京都きものパスポート」もここで手に入りますので、西のエリアをめぐるなら京都駅から直行するのも良いプランですよ。
「西陣織会館」の詳細はこちら
「京都きものパスポート」の詳細はこちら
〈三条通り〉
文明開化の名残をたどる三条通かいわいを散歩
レトロ建築の宝庫、三条通
東海道の終点、三条大橋から西の三条通は明治時代の京都のメインストリート。旧日本銀行京都支店や中京郵便局などの近代建築、旧毎日新聞社のレトロなビルや老舗など、カッコいい建築物がずらりと並ぶ通りでもあります。さまざまな歴史の交錯する京都ならではの三条通の探索へいざ、出発!
三条大橋の西のたもとには鴨川を見渡すテラス席のあるオシャレなスターバックス。スタバの西隣には老舗の駄菓子屋「船はしや」と昔ながらの日用品を扱う「内藤商店」が並びます。古い町屋の店先には棕櫚の箒やタワシがディスプレーされ、行き交う人の注目を集めています。安藤忠雄設計の「TIME’Sビル」を横目に柳並木の高瀬川を渡るとじきに現代のメインストリート河原町通に出ます。
ここからはしばらくアーケード。みやげもの屋や飲食店の並ぶなか、新京極を過ぎると寺町通にさしかかります。南西にはすき焼き屋の老舗「三嶋亭」の堂々とした店構えが現れます。1階では精肉店が営まれ、京の奥方たちがお買い物しています。今日帰るというタイミングならぜひここで牛肉を買って帰りましょう。ここのお肉はこま切れまで本当に美味しい。はす向かいの角にはかに道楽の巨大かにのディスプレーが動いています。屋根のあるアーケードはここまで。
アーケードを出ると南側に現れるのがアールデコ風の「1928ビル」 オレンジの外壁に星型の窓とバルコニーという強烈なレトロモダンビルです。1998年まで毎日新聞社の京都支局として使われていました。しゃれたカフェや洋品店が並ぶなかで、ひときわ目を引くのが「家邊徳時計店」の重厚なレンガ造りの建物。現在はブティックとして営業しています。
お隣にはパリの街角のような「ジャン・ポール・エヴァン」のカフェ。京都はチョコレートショップの激戦区でもあります。
「船はしや」の詳細はこちら
「三嶋亭」の詳細はこちら
「ジャン・ポール・エヴァン 京都本店」の詳細はこちら
買い物熱が高まる老舗の名品の数々
分銅屋のはす向かいには、いい香りを振りまく匂袋の「石黒香舗」 三条通の一本南、六角通の「宮脇賣扇庵」で憧れの京扇子も手に入れたいし、一本北の姉小路通には日本画の画材を扱う「彩雲堂」があるから墨や顔彩も買いたい……。三条通かいわいは、物欲との困難な戦いが待ち受けるデンジャラスゾーンなのです。
お買い物が一段落したら京の名物カフェ、「イノダコーヒ」でブレイクといきますか。「コーヒー」じゃありませんよ、「コーヒ」です。
「石黒香舗」の詳細はこちら
「宮脇賣扇庵」の詳細はこちら
「イノダコーヒ 三条支店」の詳細はこちら
京都の歴史を展観する通称「文博」
高倉通の角にはビッグスポット「京都文化博物館」 旧日銀京都支店を歴史博物館として利用しています。館内には歴史資料の展示のほか、京の昔の街並みを再現した「ろうじ店舗」があり、ショッピングやグルメが楽しめます。
文博からさらに三条通を西へ進むと烏丸通にぶちあたります。ここまで来たら、すぐ南には「六角堂(頂法寺)」がありますからお参りしていきましょう。そう、ここは華道家元池坊の本部があるところ。六角堂の住職は代々池坊が務めているのです。こぢんまりとした境内に隣接するのは、池坊本部の近代的な高層ビル。このミスマッチこそが京都らしい風景といえます。
ここから先の三条通は、堀川通に出るまで落ち着いた京の街並みが続きます。堀川通から先はまたアーケードのある商店街になりますが、その商店街のお話はまた後日、お伝えしたいと思います。
「京都文化博物館」の詳細はこちら
「六角堂(頂法寺)」の詳細はこちら
〈宇治〉
10円玉でおなじみの「平等院鳳凰堂」

京都の南部にある宇治へは、京都駅からJR奈良線で20分ほど。風光明媚な宇治川のほとりに立つと、かつて平安貴族がこの地を愛した気持ちがよくわかります。まずは世界遺産「古都京都の文化財」の一つ、「平等院」を目指しましょう。
お茶のいい香りのする参道を歩き平等院へ
極楽浄土を模して造営された庭園には、阿字池に面して羽を広げたように建つ鳳凰堂が優美な姿を見せています。往時は広大な寺域を有し大伽藍が建ち並んでいましたが、ことごとく焼失し、残っているのはこの鳳凰堂だけ。
堂内には金色の巨大な阿弥陀如来像が安置され、穏やかな表情で蓮の花に座しておられます。
この阿弥陀様のバックの壁面にはさまざまなポーズの雲中供養菩薩が浮かぶように配されていて、その美しいことと言ったら! すべて飛雲に乗っておられ、琵琶や笛など楽器を奏するものや合掌するもの、舞う姿など、優雅に阿弥陀様をバックアップしています。もちろんすべて国宝。これを見るためだけに宇治まで来てもバチは当たりません。当たり前か。
池の周りを巡ると、対岸から阿弥陀様の金色のお顔が拝めるように格子が丸くくり抜かれているのがわかります。平安人は極楽浄土を再現するために、いろいろな工夫をしていたんですね。境内にある平等院ミュージアム鳳翔館では雲中供養菩薩を含め、寺宝の仏像などを多数展示しています。展示方法も最新技術を駆使した幻想的な演出で、栗生明設計の建築共々、見応えのあるミュージアムです。ミュージアムショップもセンスが良く秀逸。買い物しすぎに注意です。
宇治のお目当ての一つ、お茶をいただく

平等院の境内にも茶房があり、お茶やお菓子がいただけますが、すぐ近くに宇治市営の茶室、対鳳庵があるので今回はこちらへ。宇治茶の振興と茶道の普及を目的に建てられた本格的な茶室で、平等院の鳳凰堂に相対していることから、「対鳳庵」と名付けられました。
本場の宇治茶に季節のお菓子を添えてお点前をしてくれます。お点前体験もありますよ。
近辺には福寿園や中村藤吉など有名どころのショップが多数点在し、お茶の香りを振りまいています。お茶菓子も美味しいものがたくさんあって目移りしますが、素朴な茶だんごは押さえておきたいものの一つです。深いグリーンのおだんごはお茶の味が濃く、香ばしさを感じます。
「平等院鳳凰堂」の詳細はこちら
宇治にあるもう一つの世界遺産「宇治上神社」を参拝
平等院のある宇治川西岸から中洲にある宇治公園に渡り、さらに赤い朝霧橋を渡って対岸へ。すぐに「宇治神社」の鳥居がありますので、まずはこちらを参拝。川沿いの道からさわらびの道に入り「宇治上神社」を目指します。宇治上神社は驚くほど小さな神社で、なぜここが世界遺産に? と思うかもしれません。しかし小さな門をくぐるとそこは清浄な空気が張り詰め、しんしんとした霊気を感じる神域です。拝殿の後ろにある本殿は現存する最古の神社建築。拝殿、本殿ともに国宝です。祭神は菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)。応神天皇の皇子ですが、兄に皇位を譲るため自らの命を絶ったという悲しい逸話が残っています。皇子の名前が宇治の地名の由来です。宇治上神社の境内には宇治七名水の一つ桐原水(きりはらみず)が湧いています。
「宇治神社」の詳細はこちら
「宇治上神社」の詳細はこちら
小説の舞台にもなった茶屋で茶そばを
宇治上神社をあとにして、さわらびの道を辿り、宇治橋のたもとにある「通圓(つうえん)」で、お昼に香り高い茶そばをいただきましょう。創業はなんと1160年という歴史ある通圓は、吉川英治の小説『宮本武蔵』の舞台になったことでも知られています。
「通圓(つうえん)」の詳細はこちら
『宇治十帖』の世界観にひたる
宇治は『源氏物語 宇治十帖』の舞台でもあります。一帯には紫式部の石像や匂宮と浮舟カップルの像など物語にちなんだモニュメントが点在し、「宇治市源氏物語ミュージアム」では源氏物語を視覚的に体験できるコーナーなど充実した展示と豊富な資料が揃います。ちょっとこわい伝説のある「橋姫神社」もひっそりと佇んでいます。
「宇治市源氏物語ミュージアム」の詳細はこちら
観音様の慈愛にふれる三室戸へ
さて、「通圓」でテイクアウトした抹茶ソフトを手に京阪宇治駅へ。ここからバスで「三室戸寺」へ向かいます。ここはあじさいの名所。山あいに建つ境内にはあじさい園があり、梅雨時には斜面があじさいで埋め尽くされます。西国三十三所の札所でもあり、季節を問わずさまざまな花が迎えてくれるあたたかなお寺です。
「三室戸寺」の詳細はこちら
夜は中華風精進料理で
京阪三室戸から一駅の黄檗で降りると、そこは「黄檗山萬福寺」の門前です。萬福寺は中国明朝様式の伽藍が建ち並ぶ、中国風のお寺。いんげん豆をもたらした隠元禅師が造ったお寺です。朝夕のお勤めの時間になると、鉦や太鼓をじゃんじゃん鳴らす賑やかな読経が始まります。
実はここまで来た目的は「普茶料理」というこれまた中国風の精進料理。日本の精進料理とは趣の違う、カラフルでボリュームたっぷりな精進料理なんです。
おなかがいっぱいで帯が苦しくなったら、腹ごなしに境内をちょっとぶらぶら。
あとは早く帰ってゆっくり休みましょう。おやすみなさい。
「黄檗山萬福寺」の詳細はこちら
〈会社案内〉
水持産業株式会社
https://www.warakuan.jp/
〒933-0804富山県高岡市問屋町20番地
TEL:0120-25-3306
理念:世の為、人の為、共に働く仲間の幸福と成長のために
目標:着物で笑顔がいっぱいに、地域に愛される会社・最大売上最小経費を実践し、次世代(みらい)へ繋ぐ
各SNSではお役立ち情報・最新情報を更新中ですˎˊ˗
ぜひフォローして投稿をチェックしてください🔍
種類豊富・高品質なきものをお気軽にレンタル!
〘きものレンタルわらくあん〙
@kimono_warakuan

確かな品揃え、ご購入をお考えの方にオススメです🌷
〘きものサロンみずもち〙
@kimono_mizumochi