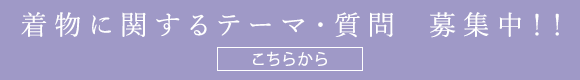海外「茶道デモンストレーション」:富澤輝実子|わらくあんみずもちsince1941 富山
机のまわりを整理していましたら数年前まで行っていた海外「茶道デモンストレーション」の写真がたくさん出てきましたので、そのお話をいたします。
在外公館からのお招きでその国に赴き、日本文化を実演でご紹介するのですが、私達のチームは「茶道のデモンストレーション」がミッションでした。
茶人の桂宗裕先生からある時、「ね~ぇ、外国人に着物着せ付けられる?」と尋ねられました。
私は外国人も日本人も着付け方は同じと思いましたが、念のため「着付けられると思いますが、どちらの国の方?」と聞きました。すると、「エストニアの方」ということでした。
その頃、エストニア人で知っていたのは大関・把瑠都(バルト)ただ一人。あの大きな把瑠都関の姿を思い浮かべて「ちょっと私の手に負えないかもしれないわ」と答えました。腰紐を結ぶ際に手が回らないと思ったのです。
桂先生が「把瑠都関に着付けるわけじゃないわよ」とおっしゃったので互いに安堵して笑い合い、バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)での「茶道デモンストレーション」のお話しが始まりました。
3か国で計10数回の「茶道デモンストレーション」を行う計画です。
内容を考えるうちに、やはり、現地で茶会のお手伝いをして下さる女子大学生や通訳などのスタッフに着物を着せてあげたいとの気持ちが高まり、短時間に手早く実演の準備をするため、ヘア・メイク・着付けのできるプロにチームに入っていただくことになりました。
いつも撮影でお世話になっている美容家の松原志津枝先生と3人でチームを組むことになりました。
〈エストニア〉
エストニアに出発!
茶道に関する準備は桂先生がなさり、着物に関しては松原先生と私がすることになりました。
現地で実演する茶会のスタッフは日本文化を学ぶ女子大学生を中心に各国約10名です。
振袖と若向きの小紋に帯と小物を合わせてセットし、船便で送りました。そのほか自分で着る着物も何セットかこしらえて準備しました。
さて出発当日です、成田からフィンエアー(フィンランド航空)でヘルシンキまで行き、トランジット。ヘルシンキ空港に着陸の際、窓の外に見えるのはおとぎ話に出てくるような「森と湖の国」。あまりに美しくて胸が高鳴りました。
エストニアに到着!
前回はフィンエアーでフィンランドの首都・ヘルシンキに到着して入国審査を終え、いよいよ目的地エストニアの首都・タリンに向けて出発するところまでお話ししました。今日は、続きをお話しします。
エストニアはバルト三国の一番北にある国で、北欧の風情が感じられる清潔な国です。現在はIT先進国で知られ、2018年には安倍首相もエストニアを訪れていらっしゃいます。
タリンの空港に到着した私たちを大使館の方が待っていてくださいました。大使館に伺って大使と大使夫人、文化担当のスタッフの方々とご挨拶ののち、早速「茶道デモンストレーション」の打ち合わせです。大使館すぐ隣の大使公邸が最初の会場でした。広やかな応接間に四畳半分の畳を敷き、茶室の雰囲気に調度を整えます。おおよその茶道具は大使館の備品で間に合いますから、点前座に茶道具一式を準備し、水屋の用意も怠りなく進めます。床の間に見立てた壁面に茶掛けを飾り、その前が正客の席です。周りにご来賓の椅子席を設えました。ふすまなどの建具はありませんから、亭主や客の様子は来賓からよく見えます。主賓は当時の現職大統領夫人、お隣は前大統領夫人です。続いて閣僚と夫人や令嬢、駐エストニア各国大使と夫人などの外交団が並ばれました。
「茶道デモンストレーション」の準備
茶会のデモンストレーションが始まります。お正客の駐エストニア日本国特命全権大使夫人がお席入り。続いて次客(詰めも兼務)の富澤が席入りしました。ひと呼吸置くと半東役の松原志津枝先生が小振袖姿でお菓子を運んでいらっしゃいました。
日本から亭主の桂宗裕(かつら・そうゆう)先生が手持ちで運んできたお干菓子です。来賓席にもお菓子は運ばれています。ほどなく茶道口に亭主が水指を前にお座りになってご挨拶。
主客ともにお辞儀をすると来賓席はシンと静まり、茶道の雰囲気になりました。亭主の桂先生は語学堪能で美貌、お人柄も抜群の茶人で知られる方ですが、お点前は水の流れのように滑らかで、日本画を見る心地で進みました。
正客は亭主の勧めにこたえてお菓子をいただき、干菓子盆を次客に送りお茶を待ちます。一服目が正客の前に運ばれて服加減の挨拶が済むと、陰点(かげだて)の薄茶が賓客に次々と運ばれてきます。
皆様、ほぼ初めての茶道体験だったと思いますが、お茶とお菓子を味わうこととともに、茶席で出会う書、画、陶芸、漆芸、木工、竹工芸、染織工芸などの品々、そしてお辞儀に代表される作法に込められた「日本」あるいは「日本らしさ」を感じていただけたようでした。その時の大統領夫人、前大統領夫人、大使夫人にお着物を着付けたのが松原先生でした。富澤はアシストにつきました。素晴らしい着物姿は大統領夫人のフェイスブックに掲載されてとてもお喜びのご様子が伝わってきました。
大満足の結果に!
エストニアでは国立美術館や国立図書館、大学の講堂など計7か所で「茶道デモンストレーション」を行いました。
大使公邸での「茶道デモンストレーション」とは異なり、お客様は100名単位で大勢様です。お手伝いに現地の女子大学生がボランティアで集まって下さいました。そのお嬢様たちに着物を着ていただきたくて、持参した振袖などを毎回汗だくになりながら着せ付けて、陰点の薄茶のお運びをしていただきました。
女学生はたいてい元気溌剌な体形です。胸も腰もボリュームがあって魅力的ですが、着物の着付けには工夫が必要です。
松原先生はそれを見越して「長襦袢は難しいのですべて半襦袢使用」さらに「半襦袢の脇縫いはほどいて自由」にし、どのような体形の方にも対応できるよう工夫したものを手作りされました。
なんとそれは大正解! 襦袢の衿が開いて困るということがなかったのです。どのお嬢様も本当に可愛い着姿になって支度をした私達も大満足しました。
〈ラトビアからリトアニア〉
EUに加盟している国は出入国審査どころか国境さえよくわからないくらい、国の移動が楽に行えました。
私たち一座(裏千家茶道教授の桂宗裕先生を座長と仰いで美容家の松原志津枝先生と私・富澤輝実子〈私も実は他流ですが茶道教授〉が座員の桂宗裕一座)と愉快な名前を付けて海外旅回りの緊張をほぐしていました。
私達はどちらの国でもデモンストレーションでボランティアをしてくださる女子大生たちに着ていただく振袖・帯・小物のセットをおよそ10人分持参するものですから、実はすごい荷物です。
日本から送るときは巨大な荷物を船便に載せていたのですが、途中での国から国への移動は陸路を自動車で行います。バルト三国に伺ったのは9月でしたから、ヨーロッパ北部とはいえまださほど寒くはなく、陽気の良い季節でした。
まさかのハプニング
ラトビアで数か所茶道のデモンストレーションを終えて、リトアニアに移動する際のことです。地図で見ると小国に見えますが車で移動となると行けども行けども果てしなく地平が続く感じなのです。途中に見えるのは干し草の大きなドラムと馬と牛でした。人も家も見えないところを朝から走り続けているうちに夕暮れが迫ってきました。夕暮れ時って少し不安になる時間帯ですよね。そんな中でなんと車がエンストしました。周りは平原、人っ子ひとり見当たりません。私達一座の3人は「まさかここで夜を越す?」と青ざめましたがドライバーは慣れているのか慌てる気配もなく、粛々と作業をしてくれて、結果何とかなりました。
〈リトアニア〉
リトアニアでの「茶道デモンストレーション」
リトアニアでは首都・ビリニュスと古都・カウナスで「茶道デモンストレーション」を行いました。カウナスは第二次世界大戦中に「命のビザ」で多くのユダヤ人を救ったことで皆様ご存知の外交官・杉原千畝(すぎはらちうね)が務めた領事館(現在は記念館)にも伺いました。
その時の写真の一つが古城を背景にしたものです。
また、翌年、リトアニアと隣国・ベラルーシで「茶道デモンストレーション」を行った際の写真が『美しいキモノ』2015年春号に掲載されましたので、添付いたしました。リトアニアでは女子大生、ベラルーシでは女子大生のほかに小学生のお嬢ちゃんたちにも、お菓子のお運びを着物姿で手伝っていただきました。とっても愛らしい姿ですので、見ていただきたいです。

茶道と着物の持つパワー
どちらの「茶道デモンストレーション」でも茶道はもちろんですが着物にも多大な興味と関心が寄せられ、茶道と着物の持つパワーを実感させられます。茶道と着物が日本にあることを本当に有難いことだと感じます。
また、同じページに大日本蚕糸会の「純国産宝絹展」が紹介されていますので、一緒に見ていただけると嬉しいです。
リトアニアには2年続けて茶道デモンストレーションに伺いました。大使館の方々と女子大学生の皆さんのお世話になりながら、私達いわば「桂裕子一座」は茶道のご紹介をしました。
〈日本の外交官:杉原千畝氏〉
カウナスという古都でも日本文化をご紹介しましたが、こちらは「命のビザ」で名高い日本の外交官・杉原千畝氏がサインし続けた旧領事館に立ち寄りました。
現在では新しく建て替わっているようですが、私達が立ち寄ったときは昔のままの比較的小さく古びた(ですがゆかしい)建物でした。
中には杉原氏がいらしたときのままに机や筆記用具、日本の国旗や地図などが保存されていて、杉原氏がビザに署名される際に、ユダヤ人一人一人に言ってほしいと頼んだ言葉も紹介されていました。
ユダヤ人の方々は日本を経由してアメリカやカナダ、オーストラリアなど各国に向かうためのトランジットビザを発給されました。
杉原千畝氏のことを詳しく知りたい方は是非出身地の岐阜県加茂郡八百津町にある「杉原千畝記念館」か、東京の飯倉にある「外務省外交史料館」へいらっしゃることをお薦めします。「外務省外交史料館」はどなたでも入れます。中に「杉原千畝記念室」があります。写真を見ながら解説を読むと当時の国際情勢や杉原氏の苦悩が伝わってきてジーンとします。私もしばらく泣きました。もちろんリトアニアの旧領事館でも泣きました。
〈ベラルーシ〉
次に移動した国は「ベラルーシ」
この後、2年目に伺ったときにリトアニアの次に移動した国は「ベラルーシ」でした。
ベラルーシでも女子大学生、現地で日本文化を紹介していらっしゃるガエフスキーさんご一家のお世話になりながら、大使館主催の「日本の秋」という日本文化紹介行事で「茶道デモンストレーション」と「着物を通しての日本文化紹介」をしました。
「着物を通しての日本文化紹介」は、日本ではどんなときにどんな着物を着ているのかを、年中行事と人生行事を例に挙げながら、着物の実物をお見せしながら説明をしました。
ベラルーシには日本文化に興味と親しみを持っている方が多く、デモンストレーションはどこも満席です。着物愛好家も大勢いらっしゃって、会場には着物姿の女性がたくさん見うけられました。そして、着物についての質問もたくさん出ました。
ベラルーシでは、首都のミンスクとヴィーチェブスクで「茶道デモンストレーション」を行いました。
ヴィーチェブスクは画家のマルク・シャガールの生まれ故郷で有名です。記念館の扉を見てびっくりしました。
赤茶色のドアなのですが、シャガール作品の中で描かれているのを見たことがあったからです。
作品を見た時には、その赤茶色の小さな四角いものが何かわからず、メインに描かれている飛んでいる馬や、花を持っている女性に見入っていたのです。また、お父様が馬を使って魚を売るお仕事だったともうかがいました。
「あ~、それで絵の中に馬が飛んでいるんだわ」と理解できて、なんだかとっても身近に感じるようになりました。
日本に帰ってきてから、シャガール展があるとヴィーチェブスクで見たシャガールゆかりの品々を絵の中で探します。見つけると周りの方にお話ししたくなって気持ちがうずうずします。
ベラルーシの茶道デモンストレーション
ベラルーシでは首都・ミンスク、古都・モギリョフでも私達「桂裕子一座(?)」は茶道デモンストレーションの機会がございました。ここでは女子大生だけでなく小学生のお嬢様がお手伝いしてくださいました。着物を着付けると、まあ、本当に愛らしくて抱きしめたいほどでした。
記念写真を撮っていただきましたが、ベラルーシの民族衣装姿の女性がステージに登場してくださり、抜群の雰囲気になりました。記念写真をご覧ください。

〈ロシア〉
ベラルーシの次に向かったのはロシア・サンクトペテルブルクです。
ミンスクの空港を飛び立ちサンクトペテルブルクの空港に到着。どこの空港でもある入国手続き、パスポートチェックがなく、す~っと外に出られたのです。不安でしたので尋ねると、ベラルーシとロシアの二国間は国内移動の扱いということでした。安心しました。
サンクトペテルブルクの町
サンクトペテルブルクの町を「パリくらいかな?」と勝手に想像していたのですが、いえいえ、とてつもなく広い町です。だって、空港から車で町に入ってから、行けども行けども町が終わらないっていう印象でした。街並みは整然として美しく、建物は伝統を感じさせるゆかしさが薫ります。素敵なところでした。
日本文化の紹介
サンクトペテルブルクでは、劇場や図書館などで茶道の紹介を中心にして、日本文化の紹介をしました。
日本文化紹介は私の担当です。お客様は80名くらい。「日本ではいつ、だれが、どのように民族衣装を着ているのか」を年中行事と人生行事を例に挙げてお話ししました。
たとえば、結婚式ではだれが、どのような衣装で出席するかを、私の白無垢をポールに掛けて見せながらの解説です。通訳の女性はロンドンで日本文化を研究している方で、素敵な方でした。

お話しの最後に質問を受けたのですが、次々手が挙がって、答えているうちに時間が無くなり(セレモニーの時間が迫っていたため)私はあわてました。でも「ここまで」と言って打ち切る勇気がありません。
しょうがないので、思い切って大きな声で「私の年代の日本人なら誰でも知っているロシア民謡歌いま~す!」と言って、「り~んご~のはなほころ~び か~わもにかすみたち~」と歌曲の「カチューシャ」を手をたたきながら歌いました。
歌い終わるといっせいに拍手がおこり、私も手をたたいて無事にお話を終えることができました。
その時の写真が「サンクトペテルブルク総領事館」のfaceBookに掲載されましたのでご紹介します。

少し、自由時間がありましたので、憧れのエルミタージュ美術館に行きましたので、その写真も何点か添付してみます。


〈富澤輝実子プロフィール〉
染織・絹文化研究家:富澤輝実子(とみざわ・きみこ)
1951年(昭和26年)新潟県生まれ。婦人画報社入社。『美しいキモノ』編集部で活躍。
副編集長を経て独立、染織・絹文化研究家として活動。誌面「あのときの流行と『美しいキモノ』」連載。
婦人画報社:現ハースト婦人画報社https://www.hearst.co.jp/

美しい着物編集部での活動
昭和48年:婦人画報社(現ハースト婦人画報社)入社、美しいキモノ編集部に配属。
入社した頃はまだまだ着物業界華やかなりし時代で、毎号超一流のカメラマンが超一流の女優さんをモデルに最高の着物姿を撮影してくださいました。
この時代は、貸しスタジオがさほどありませんから、ご自分でスタジオを構えているカメラマンのところに伺いました。
最も多く行ったのは麻布霞町(現在の元麻布)にあった秋山庄太郎先生のスタジオでした。
「本格派のきもの」というテーマでは大女優、名女優が毎号お二人出てくださいました。
当時の編集長がページの担当で私たち新人はアイロンかけのために同行。
当時のバックナンバーを見てみると、岡田茉莉子さん、十朱幸代さん、小山明子さん、星由里子さん、佐久間良子さん、三田佳子さん、司葉子さん、有馬稲子さん、岸恵子さんなど錚々たる方々です。
取材
産地取材:明石縮、伊勢崎銘仙、越後上布、江戸小紋、大島紬、小千谷縮、加賀友禅、京友禅、久留米絣、作州絣、塩沢紬、仙台平、秩父銘仙、東京友禅、西陣織、博多帯、結城紬、米沢織物など各地に。
人物取材:「森光子のきものでようこそ」の連載。森光子さんが毎号おひとりずつゲストを迎えて着物姿で対談をしていただくページで、浅丘ルリ子さん、池内淳子さん、千玄室大宗匠、中井貴一さん、人間国宝の花柳壽楽さん、東山紀之さんなど華やかなゲスト。
海外活動
娘時代から続けてきた茶の湯の稽古が思いがけず役に立つときがやってきました。
海外における「ジャパニーズ・カルチャー・デモンストレーション」のアシスト。
バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、ベラルーシ、ロシア・サンクトペテルブルク
日本文化の普及活動のお手伝いをしています。
講師として
大学や専門学校で「日本の染織」「着物現代史」「世界の民族衣装」の授業を担当。
NHKカルチャーでは「着物の基本」をレクチャー。
早稲田大学の「早稲田のきもの学」の講師。
〈会社案内〉
水持産業株式会社
https://www.warakuan.jp/
〒933-0804富山県高岡市問屋町20番地
TEL:0120-25-3306
理念:世の為、人の為、共に働く仲間の幸福と成長のために
目標:着物で笑顔がいっぱいに、地域に愛される会社・最大売上最小経費を実践し、次世代(みらい)へ繋ぐ
各SNSではお役立ち情報・最新情報を更新中ですˎˊ˗
ぜひフォローして投稿をチェックしてください🔍
種類豊富・高品質なきものをお気軽にレンタル!
〘きものレンタルわらくあん〙
@kimono_warakuan

確かな品揃え、ご購入をお考えの方にオススメです🌷
〘きものサロンみずもち〙
@kimono_mizumochi