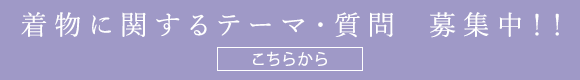〈兵庫県神戸市おすすめスポット〉
国際色豊かな神戸で着物を着るということ。
港町神戸には、世界中からやってきた様々な国の人々が暮らしています。
他国の人が着ている民族衣装も様々。
この街で日本の着物を着ていると、とても誇らしい気持ちになります。
日本人でよかった。着物というすばらしい民族衣装があってよかった。
つくづくそう思ってしまうのは、国際都市・神戸のマジックなのでしょうか。
着物姿の映える街並み 「北野異人館街」と「神戸旧居留地」、個性豊かな洋館が建ち並ぶ神戸の観光名所。

「神戸北野異人館街」
新神戸駅を降りてすぐ、港を見下ろす山の斜面に「神戸北野異人館街」が広がっています。
坂道にはコロニアルスタイルの洋館が点在し、散策するだけで異国に紛れ込んだエトランゼ気分を味わえます。
異人館街でひときわ目を引くランドマーク的存在は風見鶏の館。
ドイツ人貿易商ゴッドフリート・トーマス氏の自邸として建てられた、レンガの外壁と尖塔の風見鶏がシンボリックな洋館です。
館の目の前が広場になっていて、散策する人々の憩いの場になっています。観光案内所もここにあるので、何かと便利な場所なのです。
次に有名なのがうろこの家。
外壁を覆う天然石のスレートの形状が魚のうろこに見えることからこの名で親しまれています。
うろこの家は神戸で最初に公開された異人館で、絵本から抜け出てきたような外観が人気です。
西隣の展望ギャラリーでは、マティスやユトリロなどの近・現代絵画を常設展示しています。
ペールグリーンの外壁が美しい萌黄の館、窓の鎧戸が可愛いベンの家、イングリッシュガーデンの美しい英国館、チューダー様式の外観が個性的な山手八番館など個性豊かで美しい洋館が建ち並びます。
重厚な調度品で飾られた内部を公開している館や美術品を展示している館も多く、街全体が写真映えするスポットであふれています。
着物姿で街を歩けば明治・大正の時代のはいからさんそのもの。草履で坂道を歩くのはちょっと大変ですが、休憩できるポイントがたくさんあるから安心です。
「神戸北野異人館街」の詳細はこちら
「神戸布引ハーブ園」
新神戸駅方面へ戻ってロープウェイに乗れば緑豊かな「神戸布引ハーブ園」に到着です。
10分間の優雅な空中散歩は、神戸市街と海を見渡す絶景遊覧。
園内は四季折々に花咲き乱れる12のガーデンが整備され、ハーブたっぷりのメニューが味わえるレストランや足湯、ハーブミュージアム、ハーバルマーケットなどグルメやおみやげ探しにも最適な施設です。
もちろん写真映えもばっちり。ハーブの香りに包まれて幸せな気分になる散策が楽しめます。
「神戸布引ハーブ園」の詳細はこちら
「神戸級居留置」
ヨーロッパの都市設計により造られた「神戸旧居留地」

神戸市役所から西、大丸神戸店までの一角が「旧居留地」です。
神戸港の開港後に建設された居留地は、碁盤の目状に整然と区画割りされた美しい街。
北野異人館が個人の邸宅として建設されているのに対して旧居留地は現在、超絶オシャレなビル街となっています。
阪神・淡路大震災で被害を受けたビルも再建され、かつてよりさらに近代的な街の姿を見せています。
ブランドショップのウインドウや、カラフルなファサードが彩る垢抜けた街並みは、博物館やミュージアムを備え、知的好奇心も満足させてくれます。
大丸の西には南京町があり、街の表情はがらりと一変します。
極彩色があふれる活気に満ちたチャイナタウンには美味しそうな匂いが立ち込めて、急におなかがすいてきます。
とりあえず老祥記の豚まんを買い食いして、本格的に食べるお店を探しましょう。
「神戸旧居留地」の詳細はこちら
「クルージング」
ここまできたら船にも乗りたい

せっかく港町まできたのだからクルージングも楽しみたい。
神戸湾内をめぐるミニコースから明石海峡大橋をくぐるコースまで、多彩なクルーズプランがそろっています。
北野異人館街やハーブ園から見下ろした神戸の街を今度は海から眺めましょう。
ゴージャスなレストランシップでお食事しながら遊覧するのも素敵です。
「神戸ハーバーランド」
「神戸ハーバーランド」で港の景色を堪能。
船を降りたら「神戸ハーバーランド」でショッピング三昧といきましょう。
夜になれば、遊園地やポートタワーの綺麗なイルミネーションをバックにグラスを傾けて。盛りだくさんな1日の締めくくりを味わう時間です。
「神戸ハーバーランド」の詳細はこちら
〈岡山県倉敷市おすすめスポット〉
倉敷美観地区は、半径300mのエリアに見どころがたっぷりつまっています。
川沿いに並ぶ白壁の町家、美しい瓦屋根の蔵……。
江戸時代の姿そのままに残る、風情ある町・倉敷は着物旅にふさわしい場所です。
ぜひ一度、着物でお出かけしてくださいね。
白壁の街並み、川舟散策、絵になる風景だらけの倉敷美観地区。

「倉敷美観地区」
1642(寛永19)年に幕府の天領となり、備中国内の物資の集散地として栄えた倉敷。
JR倉敷駅から徒歩15分ほどのところにある倉敷美観地区は、白壁の街並みが美しいエリアです。
倉敷川のほとりには、雁木(がんぎ)や石灯籠が残り、古い建物は当時のままの姿を保っています。
倉敷美観地区を訪れたらまずは、世界的名画が集まる「大原美術館」へ。
1930(昭和5)年に開館した、日本初の西洋近代美術館でエル・グレコの『受胎告知』やモネの『睡蓮』などが展示されています。
美術館を堪能したら、街並みを散策。
倉敷といったら川舟ですよね。今橋と高砂橋の間の倉敷川を川舟で散策する「くらしき川舟流し」を楽しみます。
船頭さんから倉敷の街並みの見どころなどの聞きながら往復20分の舟散歩へ。
川面から柳並木越しに見る白壁の街並みは、歩いて見る景色とは違った趣です。(乗船料は有料です)
倉敷美観地区の主な移動手段は徒歩です。
着物でお出かけした場合、慣れていないと歩き疲れることもあるでしょう。
そんな時は、人力車で街散策がおすすめです。2人乗りで、倉敷美観地区のおすすめスポットを巡ります。
コースによって料金が変わりますので、事前に調べて予約をしておくと安心です。
舟や人力車での街散策をしたら、本町通りまで足を延ばしてお買い物へ。
江戸時代の面影残る旧街道の本町通りには、町家をリノベーションしたかわいい雑貨屋さんが並んでいます。
旅の思い出となるお土産選びに最適です。
「下津井のタコ」
倉敷グルメといったら「下津井のタコ」

旅の楽しみと言ったらグルメ!
倉敷は魚介が豊富です。瀬戸内海、とくに潮の流れの早い児島の下津井沖は県内有数の好漁場で、アナゴ、メバル、キス、マナガツオ、カレイなど一年を通して色々な魚があがります。
倉敷名物といえば「下津井のたこ」でしょう。潮流の速い下津井沖で水揚げされるたこは、身が締まり、味もおいしい! なかでも、産卵前の夏頃が特においしいそうです。刺身、煮物、天ぷらなどいろいろな味を楽しめます。
また、瀬戸内海でとれる小魚「ママカリ」も見逃せません。隣の家にママ(飯)を借りてまで食べたいほど美味しいことに由来して名づけられた小魚で、酒の肴におすすめです。素焼きにして酢醤油につける「酢漬け」や、開いて酢につけたあと寿司にする「ママカリ寿司」などが有名です。
「フルーツ」
そして、倉敷に限らず岡山県といったらフルーツです!
倉敷のカフェには、白桃やマスカットを使ったスイーツメニューがたくさんあります。みずみずしい白桃や大粒のマスカットが乗ったフルーツパフェやフレッシュジュースは、どれも極上の味。倉敷に行ったら、フルーツのデザートは必ず食べくださいね。どれも、おいしい逸品だらけです。
「撮影スポット」
着物女子のためのおすすめ撮影スポット。名建築の前で大正レトロ風の写真を!

1.倉敷館
大正6(1917)年に倉敷町役場として建てられた木造2階建ての洋風建築物。現在は観光案内所となっています。
住所:岡山県倉敷市中央1-4-8
電話:086-422-0542(倉敷館観光案内所)
営業時間:9:00~18:00
休業日:無休
料金:無料
2.倉敷物語館
江戸時代の長屋門や土蔵など、歴史的な建造物が残っています。館内には倉敷の街並みを伝える展示コーナーやカフェがあります。
住所:岡山県倉敷市阿知2-23-18
電話:086-435-1227
営業時間:9:00~21:00(12月~3月は~19:00、入館は15分前まで)
休業日:年末年始(12月29日~1月3日)
料金:無料
3.大橋家住宅
江戸時代に水田・塩田開発や金融業で財を成した大橋家の邸宅です。倉敷の代表的な町家のひとつに数えられ、長屋門や倉敷窓・倉敷格子などを備えた往時の商家の姿を現在に残す重厚な造りが印象的です。国の重要文化財にも指定されています。
住所:岡山県倉敷市阿知2-21-31
電話:086-422-0007
営業時間:9:00~17:00(4月~9月の土曜日は~18:00)
休業日:12月~3月の金曜日(祝日開館)、12月28日~1月3日
料金:大人550円、学生(中・小)350円
倉敷美観地区 夜間ライトアップ
日没を迎えると、倉敷川周辺の歴史的建造物や倉敷アイビースクエアを照らす光の演出が楽しめます。
暗闇に浮かび上がる白壁や建物が美しく、昼間とは違った魅力があります。
〈埼玉県秩父市おすすめスポット〉
着物で行きたい! 「秩父夜祭」の見どころ

「秩父夜祭」
毎年900万人もの人が観光で訪れる埼玉県秩父市。
その秩父の師走の名物、秩父市民の一大イベントが「秩父夜祭」です。
江戸時代から約300年の歴史あるこの祭りは、毎年12月2日・3日に行われます。
京都の祇園祭、飛騨高山祭と並び日本三大曳山祭りの一つに数えられ、当日は勇壮な屋台囃子とともに、笠鉾2基と屋台4基の山車が秩父の中心街を曳き回されます。
平成28(2016)年には「秩父夜祭」を含む「山・鉾・屋台行事」などがユネスコ無形文化遺産に登録され、世界中から観光客が数多く訪れるにようになりました。
「秩父夜祭」は秩父市民にとって特別なお祭り。市内の小・中・高校は休校となり、家族や友だち同士で、お祭りに繰り出します。この日ばかりは小さい子供も夜遅くまで起きていられるので、朝から大はしゃぎです。
山車や笠鉾を出す町内会の人たちは、祭り当日の数カ月前から毎週、学校や仕事終わりに集まって屋台囃子の練習に費やします。静かで寒気がピンッと張り詰めた夜に、遠くから風に乗って屋台囃子が聞こえてくると「もうすぐお祭りだ。いよいよ本格的な冬が来るな」と思うのです。
「秩父夜祭」の見どころは3日の夜半に行われる競技花火と観光スターマイン大会、そして団子坂での山車の曳き上げです。約6,000発の花火が打ちあがる中、最大20トンもの山車や笠鉾が斜度25度の急こう配の「団子坂」を上り始めると、祭りの盛り上がりは最高潮に!!観客席から大歓声があがります。
この団子坂の曳き上げを見るために、多くの人が数時間も前から団子坂付近で場所取りをします。
私は、寒空の下待ち続けるのが苦手で、この団子坂のクライマックスを見たことがありません。
「団子坂の曳き上がり」は身動きが取れないほどの大混雑で、見たい人が全国から集まる祭り最大の見せ場なのです。
秩父では、大正時代に女性たちの間で一世を風靡した「秩父銘仙」の振興に力を入れています。
そんななか、着物女子に注目を集めるイベントが秩父夜祭の期間中に開催されています。
秩父はかつて養蚕業が盛んで、「秩父絹」の産地として有名でした。
江戸時代には「秩父夜祭」とともに秩父絹の市(いち)が立ち、秩父の経済を潤したそうです。
時代とともに養蚕業は廃れていき、「絹市」はなくなっていたのですが…。
ここ数年、観光客が増えたことで2016年に「秩父夜祭絹市~ちちぶ銘仙マルシェ」として「絹市」が復活!
このイベントは観光客のなかでも、若い女性たちの支持を集めています。
かつて、絹の道と言われていた秩父神社近くの「買継商通り」と「黒門通り」で、絹関連の販売やイベントが行われ、「秩父銘仙デザインコンテスト」や秩父歌舞伎道中によるおねりなども行われ、大変にぎわっていました。
「買継商通り」と「黒門通り」をつなぐ「風の小道」ははレトロな雰囲気のある裏通りで、着物女子の撮影スポットとして人気。 お祭りの期間以外でも、カメラ女子が数多く訪れています。
「お酒とグルメ」
山車や花火もいいけど「お酒とグルメ」!

「秩父源流水」というミネラルウォーターが売られているほど、秩父は水がおいしい土地。
つまり、お酒、食べ物がおいしいのです! 秩父の名産といえば何を思い浮かべますか?
蕎麦、わらじかつ丼、ホルモン、しゃくし菜、味噌ポテト、日本酒、ワイン、ウイスキー……。
数え上げたらキリがないくらい、たくさんの名産品があります。
「秩父夜祭」に来たら、お酒やグルメも堪能したいですよね?
蕎麦もわらじカツ丼も、それぞれ地元のおいしい店は数多くありますが、夜祭を楽しみながら食事も、お酒も…と色々楽しむには時間に限りがあります。
そこで私がおすすめするのが、西武秩父駅構内にある「祭りの湯」。駅構内で温泉や食事ができる施設です。
ここは地元のお酒が試飲できるコーナーや秩父の名物が食べられるフードコートが充実しています。ここにくれば、あちこち行かずとも、蕎麦、わらじかつ丼、ホルモン、しゃくし菜、味噌ポテト、日本酒、ワイン、ウイスキー…、すべて食べたり飲んだりできます。観光も、お酒も、グルメも…と、色々楽しみたい人は、ぜひ「祭りの湯」に立ち寄ってください。もちろん、おみやげも買えますよ。
西武秩父駅前温泉「祭りの湯」の詳細はこちら
〈岩手県盛岡市おすすめスポット〉
「盛岡市中ノ橋通り」
レトロな建物と郷土の文化
「岩手銀行赤レンガ館」/「もりおか啄木・賢治青春館」

JR盛岡駅から車で約10分ほどにある通り「中ノ橋通」を歩いていると、あれれ?どこかで見たことがある建物が。
そう、あの東京駅にそっくりの赤いレンガでできた建造物は「岩手銀行赤レンガ館」です。
それもそのはず、東京駅の設計士 辰野金吾氏による設計で明治44年に完成した建物。
現在東北で残っている同氏の作品は同館のみという貴重なこの場所は2012年までは銀行でしたが、今ではコンサートや伝統工芸作品の展覧会など、さまざまなイベントが行われ地域の人々に愛されています。
そして、少し歩いた先に今度はグレーがかったレンガの建物が見えてきます。
こちらは明治43年完成の「もりおか啄木・賢治青春館」です。
入り口のアーチ状に組まれた石造りが印象的で、どこか西洋の雰囲気。
中に入ると同県出身の石川啄木や宮沢賢治を紹介する展示コーナーがあったり、タイムスリップしたような気分になる喫茶室など、のんびり過ごすことができるスポットです。コーヒーがおいしいと評判ですよ。
レンガ壁の前で記念撮影をして旅の記念に。どちらも国指定重要文化財です。
「岩手銀行赤レンガ館」の詳細はこちら
「もりおか啄木・賢治青春館」の詳細はこちら
「東家(あずまや)」
「わんこそば」で有名な「東家(あずまや)」
お昼ご飯はどこで食べようか?盛岡で食べたらいい名物は?
中ノ橋通の「東家」では、あの「わんこそば」が食べられます。
一度は体験してみたい、わんこそばに挑戦するのも良いですし、他にも「南部そば定食」、「南部そば会席」などのメニューもあります。
「東家(あずまや)」の詳細はこちら
「南昌送」
盛岡市清水町「南昌荘」 風情のある邸宅と庭園でまさに着物姿が映えるロケーションなら、「南昌荘」にぜひ立ち寄っていただきたいと思います。
明治18年頃に盛岡出身の実業家 瀬川安五郎によって邸宅として建てられましたが、その敷地内には庭園もあり、2000年から一般公開されています。
なんと言っても四季折々で表情を変える情景は美しいの一言。自然豊かな庭園の花々や紅葉、そして雪景色も見事です。
木造建築の室内に足を踏み入れると思わず心が和み、しとやかな気持ちになる情緒あふれる空間で充実した時間を過ごすことができます。
「南昌荘」の詳細はこちら
「岩手県立美術館」
広大なランドスケープが魅力
最後に、盛岡駅の西側、新開発地域の盛岡の新しい中心街に立地する「岩手県立美術館」をご紹介します。
春先から初夏にはみずみずしい緑の原っぱが広がる「中央公園」に隣接するアートスポットで、曲線が印象的な建物も迫力があります。
入館する前にも楽しみがいっぱい

自然に囲まれた景観のなかに建つ美術館は、その建物の美しさも相まって館内に入る前にもたくさん写真を撮りたくなってしまいます。
ちなみに、美術館前にある小高い山、展望台に登れば、そこは岩手山を眺めるのに最適な絶景スポットですのでぜひ立ち寄ってみてください。
晴れた日には別名「岩手富士」とも呼ばれる「岩手山」がくっきりと見えて素晴らしい眺め。
なだらかな稜線と壮大な迫力が魅力の岩手山のパワーを感じながら、記念の一枚を撮ってみてくださいね。
アート鑑賞に最適な空間
いよいよ中に入ると、その吹き抜けの空間の大きさに驚くとともに、一気に鑑賞モードの気分にスイッチが入ります。時期によって変わる企画展も注目ですが、県ゆかりの芸術家の常設展示も見応え十分。舟越保武、松本竣介、萬鐵五郎を中心に展示されています。ゆったりと鑑賞に集中できる広々とした空間、展示室から展示室に移動するアプローチも随所に雰囲気がありおしゃれです。
休憩スペースにもこだわりがちりばめられて
それから、県立美術館で密かに感動したのは、2階のライブラリー裏にある木製のベンチのスペース。
一休みと思って腰掛けたときに目の前の横に細長い窓からちょうど岩手山が見えました!
窓枠で切り取られた景色が、これこそアートと感動するとともに、ここでずっと外の景色を眺めていたい気持ちになりました。
1階にもモダンな一人がけ椅子が並ぶコーナーがあり、こちらでも外の景色を眺める形で一休みすることができます。
ミュージアムショップとレストランもお忘れなく
併設のミュージアムショップとレストランもおすすめです。
ミュージアムショップ「ガレリーナ」には企画展の図版やポストカードをはじめ、一般的なアートグッズ以外にも県内の作家が作る雑貨なども取り扱いがあり、小さなスペースですが見応えがあるラインナップ。
ついついお財布の紐がゆるみます。
レストラン「パティオ」は中央公園側がガラス張りになっているため、どの席からでも外の景色を感じながら食事ができるレストラン。
企画展にちなんだオリジナルメニューは見た目もお味も満足!
「岩手県立美術館」での心地よい五感の刺激が非日常のリフレッシュになる、すてきな時間を楽しむことができるでしょう。
「岩手県立美術館」の詳細はこちら
〈群馬県桐生市おすすめスポット〉
帯の三大産地はご存知ですか?
帯の三大産地は「博多」「西陣」「桐生」! ということで、着物好きの皆様なら「桐生」という地名を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
「桐生」は群馬県の東部に位置する自然豊かな場所。
地元で定番の「上毛かるた」では「桐生は日本の機どころ」と詠まれ、古くから絹織物の産地として知られています。
東京駅から新幹線を使って乗り継げば、2時間ほどで行ける場所です。
レトロな街にタイムスリップ 「有鄰館」・「桐生天満宮」
まずは、着物で行きたいおすすめ観光スポットのご紹介です。
「有鄰館(ゆうりんかん)」
市指定重要文化財で、かつてお酒や味噌、醤油を醸造していた三角屋根の蔵。
通り自体がとっても風情のある場所なので、着物姿で立つだけでどこかレトロなフォトジェニックな写真が撮れると思います。
日程によっては、着付け体験も出来るようで、チェックして行くとより楽しめそうです。
「桐生天満宮」
関東五大天神のうちの一つで、初詣には多くの人が訪れます。
地元では「天神さま」と呼ばれ、受験シーズンにもたくさんの人がお参りに足を運ぶのだそうです。
桐生天満宮には、龍をモチーフとした彫刻や絵画が数多くあり、特に「貴龍」が有名。
そもそも「龍」は、古来より天災・人災・病魔などの災厄や悪運を断ち、家内安全・家運隆盛をもたらす守護神です。
また「登龍門」と言うように受験合格や出世を導く吉神ということから、「昇運の神・桐生天神」とされ、数多くの参拝者が訪れているそうです。
ただ、私が行った日は平日だったこともあり、スムーズに参拝をすることができました。
なんだかとってもラッキー♪ お時間がある方は平日がオススメです。
お昼は近くに「レンガ」という三角屋根のパン屋さんがあるので、そこで済ませました。ピアノの生演奏をしていて、雰囲気もバッチリ。旅の疲れを癒やしてくれる場所でした。
「織物参考館 紫」
さて、ぜひ着物好きの方には行ってみていただきたい場所があります。
それは、桐生駅から車で5分ほどの場所にある「織物参考館 紫(ゆかり)」です。
旧鋸屋根工場や撚糸場、釜場、整経場などの建物が、展示室や体験学習室となっている「動く、さわれる、生きている」をテーマとした織物博物館で、藍染や手織りが体験出来る場所です。
地元の小学生たちが社会科見学で来ていたり、日本の企業にとどまらず海外から研修旅行で来る方も多いのだとか。
貴重な資料1,200点とともに、織物・染色技術の歴史、文化の発展の様子を学べる貴重な場所で、着物好きの方にとっては垂涎の場所だと思います。
時間を作って、手織り体験や藍染体験をしてみると、一枚の反物が出来上がるまでにどんなに時間がかかっているのか改めて実感できます。
染めたハンカチやTシャツは一生の思い出になると思いますので、夏休み等長期の休みにゆっくりとお子さんやお孫さんと訪れてみてはいかがでしょうか。
「織物参考館 紫(ゆかり)」の詳細はこちら
「ひもかわうどん」
幅10cmのうどん!?桐生のグルメ情報をご紹介いたします!
とっても幅広いうどんで10cmほどのものが多いようです。一反木綿のような見た目ですが、厚みは1〜2mmと薄いので、ツルッと食べられます。私も最初ご馳走になった時は驚きました。お箸で持ち上げると、お箸の長さの半分以上がうどんで埋まっていたので(笑) コシが強く途中で切れてしまったりせず、もちもち。最後まで美味しくいただきました。
ちなみに私が行ったお店はこちら
「味処ふる川 パークイン桐生店」
「ソースカツ丼」
一般的なカツ丼との違いは、卵でとじていないこと。
小さな丸いヒレカツを甘いソースにくぐらせて、ご飯の上にのせた一品です。キャベツなどものせず、シンプルなのが印象的でした。
サクッとした衣で揚げていて、脂身の少ないヒレカツを使用しているので、女性でもあっさり美味しくいただけました。
一つひとつのヒレカツも小さいので口に運びやすく、ソースで口元を汚さずに食べられるのも嬉しいですね
ちなみに私が足を運んだお店はこちら
「志多美屋」
黄色い建物で遠くからでもとっても目立っていました!
「焼きまんじゅう」
テレビでも紹介されたことのある、群馬名物の「焼きまんじゅう」はぜひチェックしていただきたいおすすめです。
蒸して作った餡の入っていないお饅頭を串に刺して、甘い味噌ダレをつけて焼かれています。
てっきり最初は、「おまんじゅう」なのであんこが入っていると思って食べたので、何も入っていなくてびっくり(笑) 地元ではおやつとして、そしてお祭りの屋台の定番となっているのだそうです。
素朴な味わいで、どこか懐かしさを感じる「焼きまんじゅう」 着物で食べるのはタレが袖についてしまいそうでちょっと怖いかも……、と思いますが、地元の子供達はお祭りで浴衣を着て食べているのですから、意外と大丈夫なのかもしれません。今回いただいたのはこちらのお店
「前沢屋」
帰りは新桐生駅を利用したのですが、駅には地元のお祭り「桐生八木節まつり」の人形がかざられていました。
毎年8月に3日間開催されるお祭りで、去年は述べ565,000人もの方々が足を運ばれたそうですよ! 夏に浴衣でお祭りに参加するのも楽しそうですね。
〈富山県高岡市おすすめスポット〉
「高岡大仏」
高岡大仏は日本三大仏(諸説あり)の一つであり、日本一イケメンの大仏ともいわれています。
その由来は歌人の与謝野晶子が「かまくらや御(み)ほとけなれど釈迦牟尼(しゃかむに)は 美男(びなん)におはす夏木立(なつこだち)かな」と鎌倉大仏とイケメンと詠ったが、その後に高岡市に訪れ、高岡大仏を拝し、「鎌倉大仏よりイケメン」とおっしゃったとか…
現在でも口コミなどで高岡大仏はイケメンと広がりつつあります。
そんな高岡大仏ですが現在は三代目で、初代・二代目は大火により消失しています。三代目の高岡大仏は高岡の伝統工芸「高岡銅器」の職人さんたちの協力のもと建立されました。
銅器職人さんの最高傑作ともいえる大仏様です。
高岡大仏
「金屋町」
千本格子に石畳の大変風情のある町並みで、どこか金沢のひがし茶屋街に似た街並みです。
金沢はお茶屋の街ですが、金屋町は銅器職人さんの町です。
2012年には重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
金屋町の家々は長屋で、メイン通りから『母屋→中庭→蔵→作業場』となっています。
これは銅器を製作しているときに、火災が発生してしまった場合の母屋への延焼を防ぐための対策だとか。
また、屋根には天窓という窓があり、お隣さんと家が連なっており外の光を取り入れるためつけられています。
そして、メイン通りの石畳の道には銅板が埋め込まれていて、中には星形やハート形があり、星形は北斗七星の配列になっており、ハートは数が少なく見つけるとハッピー!
金屋町
「山町筋」
金屋町とともに重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
山町筋は土蔵造りの町並みが残り金屋町とはまた違った風情を感じられます。
また、毎年5月1日に開催される御車山祭りで出される山車を所有する10の町を総称し山町とも呼ばれています。
土蔵造りの建物を見学できるのが「菅野家」。ミセノマ・ホンザシキ・ブツマなどを一般公開しています。
「菅野家」は高岡の政財界をリードした名家で、重要文化財に指定されています。
現在も住居として使用されています。
土蔵造りの建物のほかに赤煉瓦の建物があり、旧富山銀行本店として使用されていました。
旧富山銀行本店は大正3年、東京駅の設計にあたった辰野金吾の監修を受けて清水組が設計したものといわれ、県内唯一の本格西洋建築です。
御車山を紹介している「御車山会館」も見どころで、ユネスコの無形文化遺産に登録された山車を間近でみることができます。職人の技を是非堪能してください。
山町筋
「雨晴海岸」
雨晴の由来は、源義経公がこの地に来られた時、にわか雨に遭い「雨を晴らすのを待った」そうで…「雨晴(あまはらし)」と
呼ばれるようになりました。
道の駅の向かいには源義経公を祀る「義経社(ぎけいしゃ)」があります。
その下には義経一行が雨宿りしたと伝えられる義経岩があるとか…
また、この海岸からは日本三名山の一つ『立山』を眺めることができます。
このように海を隔てて3000m級の山々を見ることができるのは、世界でも3つしかなく、その中の一つに入っています。
(イタリア/ジェノバ〜マッターホルン、チリ/バルパライソ〜アコンカグア山)
しかし、立山連邦も毎日見られるわけではなく、訪れた日に見られたらラッキー☆
ここで大伴家持が詠った万葉の句を一句。
「立山に 降り置ける雪を常夏に みれどもあかず 神からならし」
(意)立山に降り積もった雪はいつでも消えることなくがなく、いつみても飽きることはありません。神々しいからなのでしょう。
雨晴海岸
「万葉歴史館」
高岡市は万葉のふるさとです。
万葉の歌人大伴家持が越中の国司として赴任しました。
万葉集は全20巻あり4516首の歌があります。
その中で大伴家持が詠った歌は473首で内220首余りが越中で詠まれた歌です。
万葉のふるさとならではのイベントも行われています。
10月第一金土日に、昼夜問わず万葉集4516首を全て詠みあげる「万葉朗唱の会」や「万葉かるた大会」が開催されています。
市内では石碑巡りや大伴家持像もあるので、着物を着て撮影すると風情のある写真が撮れるかも…!
万葉歴史館
〈石川県金沢市おすすめスポット〉
「兼六園」
日本三名園の一つ。(水戸の偕楽園・岡山の後楽園・金沢の兼六園)
兼六園は、金沢城の外庭として使われておりました。名前の由来は、時の老中松平定信が、宋の落葉名園記にも記されている、『宏大と幽邃・人力と創古・水泉と眺望』の六つ全てを兼ね備えている園という事で名づけました。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪吊りと四季を通じて楽しめます。時期によっては無料開放もしています。
兼六園
「金沢城」
江戸時代、加賀藩主前田氏の居城でした。
現在は国の史跡に指定されておりお城はないものの、石垣の博物館と言われるように貴重なものがたくさん見られるためおすすめ。
また、金沢城址公園になる前にはなんと金沢大学のキャンパスだったのです。
兼六園の隣なのでぜひ足を運んでみてください!
金沢城
「ひがし茶屋街」
新金沢には西茶屋街・主計町茶屋街・ひがし茶屋街と3つの茶屋街があり、それぞれ違った風情を味わえます。
その中でも、ひがし茶屋街は観光客の方でにぎわいます。
ひがし茶屋街は行ったことがあるという方は、ぜひ残りの2か所もめぐってみてはいかがでしょうか?
着物で写真を撮るとなると、ひがし茶屋街ではメイン通りで、柳の木の下で格子戸の建物をバックに撮るのが王道でしょう。
また、茶屋ならではの路地に入り人の少ないところで撮るとさらに風情を感じられます。
ひがし茶屋街
「寺町寺院群」
金沢の中心部にある小立野台より室生犀星ゆかりの”犀川”を渡ったところには寺町があります。
名前の通りお寺が70以上あり、まさしく寺の町ですね。
その中には、”妙立寺”というお寺があり、”忍者寺”とも呼ばれています。このお寺の中は仕掛けがいっぱいで、案内がないと絶対に迷ってしまうお寺です。
また、そのお寺に行くまでの間の道沿いに、レインボーキャンドルという珍しいキャンドルがあるお店があり十分楽しめます。そして、徒歩3分のところには先程紹介した”西茶屋街”があります。西茶屋街には、王室御用達チョコレートブランドのお店もあり、チョコレート好きにはたまりませんね。
寺町寺院群
「尾山神社」
尾山神社は、金沢の繁華街の武蔵ヶ辻と片町香林坊の間にあります。
加賀藩初代藩主前田利家を祀る神社で、神門が洋風になっており上部にはステンドガラスがはめ込まれていておしゃれです。
また、初詣の時には大変多くの参拝客が訪れにぎやかです。このおしゃれな神門の前で写真を撮るのも映えそうですね!
金沢の観光名所は他にもたくさんあり、長町武家屋敷や近江町市場、21世紀美術館など観光名所がギュッと集まっています。
どこの場所でも着物で巡るのには最適なところばかりです。
私自身、着物で金沢に訪れたことがないので、新型コロナウイルスが収まった時には行けたらいいなと思っています。
今が踏ん張りどころ!!コロナに負けずがんばりましょう!!
尾山神社
〈岐阜県飛騨地方おすすめスポット〉
「白川郷 萩町合掌集落」
1995年に、富山県の五箇山(相倉合掌集落と菅沼合掌集落)とともに、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。【白川郷・五箇山の合掌造り集落】
三つの地区の中でも一番規模が大きく180棟もあるそうです。現在でも生活を営まれています。そして観光地として多くの人が訪れています。
着物を着て、歴史的建造物の前で写真を撮ると風情がでそうですね。
ここで皆さん、合掌造りの名前の由来はご存知ですか?
ご存知の方もおられると思いますが、屋根が合掌したときの形に似ているという事からつけられたといわれております。
しかも急ですよね。これにもちゃんと理由があります。
合掌造りの屋根は60゜の傾斜で、太陽が当たりやすく萱が乾きやすい角度なんだそうです。生活の知恵ですよね。
また、あれだけ大きいのに、釘を一本も使っておらず、『ネソ(マンサクの若枝)』で縛るようです。
そして、囲炉裏ででた煙が屋根を燻し、繊維なども固くするため防虫や防腐にも役立つそうです。
この白川郷でのイベントの一つが、毎年9月の終わりから10月にかけて『どぶろく祭り』が催されます。
五穀豊穣・家内安全などを祈願します。この祭りの名前の通りお神酒として『どぶろく』が用いられます。
どぶろくというのは、『濁り酒』で日本の伝統的な酒のうち、米と米麹と水を原料とし発酵させただけで<漉す>工程を経ていないお酒です。
このどぶろくを、神社酒蔵で造ります。『どぶろくの儀』を終えた後は、おかみさんたちが来客一人ひとりにどぶろくを盃についで回ります。
また、どぶろくの振舞いは各町内で行われる神社の境内でのみです。
お酒好きにはたまらないかもですね…!
「高山」
岐阜県高山市は全国一大きい市町村として知られております。
その面積はなんと約2,178㎢で、大阪府・香川県よりも広く東京都とほぼ同じ面積なんですよ。
都府県に匹敵するぐらいの大きさなんてすごいですよね…。
しかしながら、これだけ大きい市なのに、山林が92%を占めているため可住面積は限られてきます。
そんな高山市の中心には、『古い町並み』があり観光客が絶えません。
城下町の三筋の町並みを散策でき、出格子の軒先の下には用水が流れ情緒あふれる街並みを堪能できます。
酒屋さんには酒ばやしが下がり、緑の酒ばやしだと『新酒ができました』という合図になります。看板の役目になっていますが、元はお酒の神様に感謝を捧げるものだったそうです。
他にも、旅雑誌に紹介される飛騨牛の握りずしや、みたらし団子が有名です。『飛騨牛』は本当においしいですよね!これが握りになっているなんてもう食べるしかないでしょ!!!
お店によって値段は変わってきますが、700円~お召し上がりいただけます。
『みたらし団子』は、甘いたれのみたらし団子を思い浮かばれますよね?ここ飛騨のみたらしは、しょうゆの香ばしい匂いがたまりません!!!のりが巻いてあるみたらし団子も最高!
みたらし団子は80円(のり付き+10円)とお手頃なのもうれしい。食べ歩きできるのもいいですよね♪
また、高山と言えば、春と秋の『高山祭』もありますよね!春は12台、秋は11台の山車が引き揃います。夜は提灯の明かりが幻想的で圧巻な姿をみれます。
お祭りに登場する実際の山車はこの時にしか見れませんが、『飛騨高山 まつりの森』がでは、飛騨の匠の協力のもと平成の祭り屋台を間近で見学できます。
高山祭りの歴史などを詳しく知りたい方はぜひ!!!
「飛騨古川」
“高山の古い町並みがあまりにも有名ですが、こちらの古い町並みも見どころ。
白壁土蔵の町並みに鯉が泳ぐ瀬戸川が流れ、高山とはまた違った風情を感じられます。
町には、お酒の店や和ろうそく屋さんもあり、ゆったり散策できます。
毎年4月には、飛騨古川まつりが催されます。約400年の歴史があり、2016年には全国33件の『山・鉾・屋台行事』の一つとして、ユネスコの『世界無形文化遺産』の登録されました。
よくニュースなどでも紹介されるので一度は見たことがあるのではないでしょうか?男たちの勇ましい起こし太鼓や豪華な山車などを2日間に渡って盛大に繰り広げられます。
祭り好きにはたまらないですね!”
「郡上八幡」
郡上八幡には、名水100選第一号の『宗祇水』があるところです。また、サンプルや郡上踊りの町でもあります。
郡上八幡城の城下町として栄え、現存するお城は模擬天守としては最古で、珍しい木造だそうです。
この天守閣は高速道路(東海北陸道)からも見えます。そして、お城の下には町が広がっており、サンプル製品を販売するお店や、ニッキ飴のお店などが並んでいます。
どうして郡上八幡がサンプルの町になったのかというと、岩崎瀧三(いわさきたきぞう)さんという方で、郡上八幡で生まれ育ち、大阪にて食品サンプルの事業化に成功した第一人者だからです。
その食品サンプルも、本物に見えるくらいのクオリティで、よりリアリティを出すために照明の角度などの細やかな点まで考え抜かれているそうです。お店ではサンプルの製作体験やキーホルダーやマグネットになっているものも販売されています。
旅の思い出に一つ・・・!
お祭りと言えば『郡上踊り』ですよね、7月中旬から9月上旬まで開催されます。長い!
8月13日から16日までは20時から翌4時または5時まで踊り続ける『盂蘭盆会』があるそうです。
4日間の徹夜踊りには県外の方の参加者が多く、約25万人に達します。浴衣を着てぜひ参加してみましょう!!!
そして、郡上踊りのほかに郡上八幡の夏の名物として、『吉田川の飛び込み』があります。
吉田川は、鵜飼でよく知られる長良川の支流です。
『川ガキ』と呼ばれる子供たちが、この吉田川に架かる『新橋』の欄干から飛び込むというもので、高さはなんと12m!!!!!地元の子供たちにとっては名誉なことであり、下級生にはあこがれの的だとか?!!
1996年(平成8年)には、吉田川の川遊びとして環境庁により、残したい日本の音風景100選に選ばれました。(ちなみに和楽庵がある富山県は『称名滝』、『エンナカの水音とおわら風の盆』、『井波の木彫りの音』です!)
安全確保はされているとは思いますが、必ずしも安全とは言い切れません。橋の欄干にも警告看板があるので、不慣れな方の飛込みはやめましょう!
〈会社案内〉
水持産業株式会社
https://www.warakuan.jp/
〒933-0804富山県高岡市問屋町20番地
TEL:0120-25-3306
理念:世の為、人の為、共に働く仲間の幸福と成長のために
目標:着物で笑顔がいっぱいに、地域に愛される会社・最大売上最小経費を実践し、次世代(みらい)へ繋ぐ
各SNSではお役立ち情報・最新情報を更新中ですˎˊ˗
ぜひフォローして投稿をチェックしてください🔍
種類豊富・高品質なきものをお気軽にレンタル!
〘きものレンタルわらくあん〙
@kimono_warakuan

確かな品揃え、ご購入をお考えの方にオススメです🌷
〘きものサロンみずもち〙
@kimono_mizumochi